3月に入り我が家では恒例の味噌仕込みを開始しました。まずはお米を蒸して麹を作る所から作業が始まります。

去年までSDS01.だけで作っていたのだけど、今年は過去最高の26㎏仕込むので時計型ストーブも出動させ2台体制で大量のお米を蒸し上げました。

麹作りが終盤に差し掛かった頃に、大豆戻しこれまた2台の薪ストーブで柔らかくなるまで煮込みます。

所が、なぜか時計型ストーブの方だけ沸騰しないのです。
直火じゃ無いのが原因かと思い、天板のリングを外して見ても根本的な解決になっていない様で状況が劇的に変わりません。いつまでたってもお豆が対流せずに緩やかに暖まるだけでした。
こういった違和感を感じる状況は僕が最も得意とする場面なので早速ストーブの中を覗いてみると…答えが目の前に有りました。
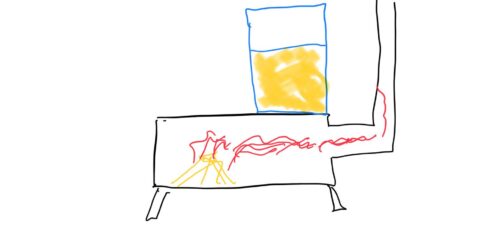
このストーブはロケットストーブに改造していたので、購入時に付属していたバッフルを廃棄してます。なので炎が天板をなめる様に流れずに煙突へダイレクトに吸い込まれていました。
なるほど、炎を衝突させないと効率的な熱交換が行われないのですね!
愛農かまどを自作したブログにあまり温度が上がらなくて困ったと書いてあった記事を読んだ記憶が有りますが、多分僕と同じ状況で炎の衝突が起こっていない構造だったのでは無いかと想像します。

対策として、工場に置いてある適当なブリキ板を煙突取り出し口の前に置き炎が直接煙突に流れない様にするとあっという間に沸騰してくれました。
こうやって記事に書くと当たり前の事なのですが、実際に現場にいると現象に囚われるばかりで問題が発生した原因を推測する事に意識を向ける事が困難だと考えます。今回は2つのストーブを並行して使用する事で違和感を感じる事が出来ましたが、時計型ストーブだけを使っていれば「こんなものかな?」とそのまま使っていたと思います。
今回得た知見ですが、炎は衝突対流させて効率よく放熱させないと、燃焼によって発生した熱が煙突から勢いよく排出されるので勿体ないと言う事です。
いやー問題の発生原因を特定して改善するって面白いです。








コメント